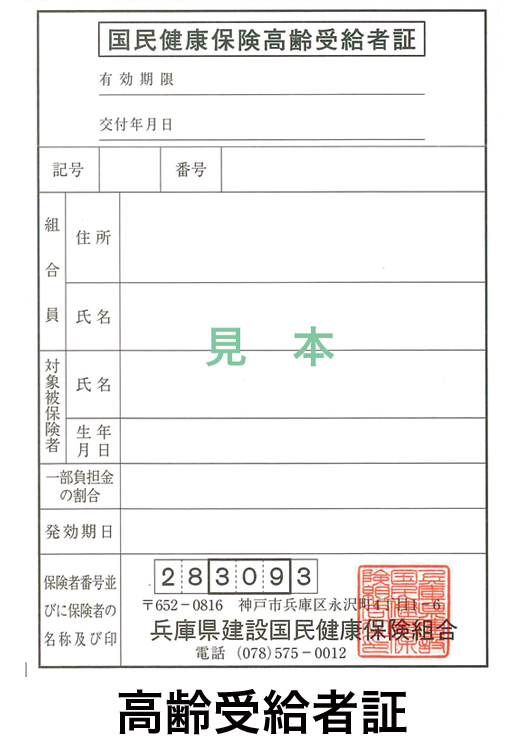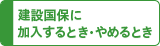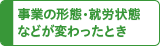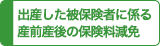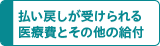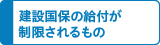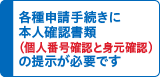70�`74�̐l�̈��
70�Έȏ�ɂȂ�ƁA����҈�Â̑ΏۂɂȂ�܂��B�����̋敪�ɂ���ĕ��S�������Ⴂ�܂��B
70�ɂȂ����Ƃ�
�@70�ɂȂ�a�����̗����P���i�P�����܂�̕��͂��̌��j����ꕔ���S���̊������L�ڂ����u����ҏv����t���܂��B
�@�u����ҏv�̕��S�����̔���ɕK�v�ȏ������́A�}�C�i���o�[���x�𗘗p���ďƉ�E�擾���܂��B�Ȃ��A���������擾�ł��Ȃ��ꍇ�́A�u�����i��j�ېŏؖ����v�̒�o�����肢�������܂��B
70����74�̐l�Ɂu����ҏv����t���܂�
�i���j�}�C�i�ی����Ƃ́A���N�ی��̗��p�o�^�����Ă���}�C�i���o�[�J�[�h�ł��B
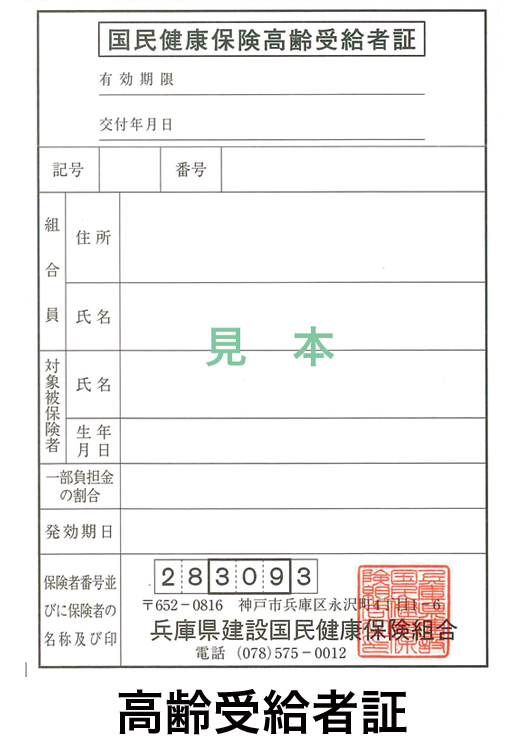
�@��Ë@�֓��̑����Ŏx�����ꕔ���S������\���������̂ŁA
��f����Ƃ��́u���i�m�F���v�܂��́u�}�C�i�ی��i���j�v�Ɓu����ҏv����������ɒ��Ă��������B
�@��Ë@�֓��́u����ҏv�ň�Ô�̕��S�������m�F���܂��B
�u�}�C�i�ی��i���j�v�Ŏ�f�̍ۂɂ́u����ҏv�͕̒s�v�ƂȂ�܂����A�@��̕s����ŁA�u�}�C�i�ی��i���j�v�����p�ł��Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA��f�̍ۂɂ́u����ҏv�y�сu���i���̂��m�点�i�}�C�i�|�[�^���̎��i����ʂ��j�v�����������������B
�u����ҏv�͖��N�W���ɍX�V���܂�

�@�u����ҏv�ɋL�ڂ���ꕔ���S���̊����́A�O�N�̏����Ŕ��肷�邽�߁A�}�C�i���o�[���x�𗘗p���ďƉ�E�擾���܂��B�i�������̎擾�ɂ��Ă� [70�ɂȂ����Ƃ�] �Q�Ɓj
75�ɂȂ��
�@75�ɂȂ�ƁA�����I�Ɍ��ݍ��ۂ̎��i���Ȃ��Ȃ�A�s���{���P�ʂŐݗ������u�L��A���v���^�c����
�u�������҈�Ð��x�v�Ɏ��i���ڂ�܂��B
�܂��A���̏�Q������65�Έȏ�̐l���F�����������ΏۂƂȂ�܂��B
| ���g������75�ɂȂ�Ɓc |
�����ɉƑ��̕������ݍ��ۂ̎��i��r�����܂��B
�Ƒ��̕��͂��Z���̎s�����ʼn����葱�����K�v�ł��B
�g�����̎葱���y�сA�g�����ƉƑ��́u���i�m�F���v�܂��́u���i���̂��m�点�v�Ɓu����ҏv�̕ԋp�͕s�v�ł��B
|
| ���Ƒ���75�ɂȂ�Ɓc�c |
�a�����̗����Ɍ��ݍ��ۂ̎��i��r�����܂��B
�u���i�m�F���v�܂��́u���i���̂��m�点�v�Ɓu����ҏv�̕ԋp�͕s�v�ł��B
�g�����Ƃ��̑��̉Ƒ��͌��ݍ��ۂɌp�����ĉ������܂��B
|
70����74�̐l�̎��ȕ��S���x�z�i���z�j
�i���j�}�C�i�ی����Ƃ́A���N�ی��̗��p�o�^�����Ă���}�C�i���o�[�J�[�h�ł��B
�@��Ô�̕��S�����x�z�����Ƃ��A�\���ɂ�蒴�������̕����߂������܂��B
| �ꕔ���S���� |
�����敪 |
�K�p�敪 |
���ȕ��S���x�z�i���z�j |
| �ʉ@�l |
����
�i���@�܂ށj |
| 3�� |
�ېŏ���690���~�ȏ� |
������݇V |
252,600�~+�i�����-842,000�~�j�~1��
��2 [140,100�~]
|
| �ېŏ���380���~�ȏ� |
������݇U |
167,400�~+�i�����558,000�~�j�~1��
��2 [93,000�~]
|
| �ېŏ���145���~�ȏ� |
������݇T |
80,100�~+�i�����-267,000�~�j�~1��
��2 [44,400�~]
|
2��
|
��ʏ����� |
18,000�~
��1 [�N�ԏ��144,000�~]
|
57,600�~
��2 [44,400�~]
|
| �Ꮚ����II |
8,000�~ |
24,600�~ |
| �Ꮚ����I |
8,000�~ |
15,000�~ |
��1�c �x���ΏۂƂȂ�A�\�����K�v�ȏꍇ�́A�x���\���̂��m�点�𑗕t���܂��B���e���m�F�̏�A�\�����Ă��������B
�Ȃ��A�v�Z���ԓ��ɉ����ی��̕ύX�Ȃǂ������ꍇ�ɂ́A���ݍ��ۂ݂̂ł͎����I�ɋ��z���Z�o�ł��܂���̂ŁA�x���\���̂��m�点�𑗕t�ł��Ȃ��ꍇ������܂��B
��2�c 12�����ȓ��ɂS��ȏ㍂�z�×{��̎x������ꍇ�i�����Y���j�̂S��ڈȍ~�̌��x�z�ł��B
�Ȃ��A�ی��҂��ς�����ꍇ��������Ă���u���сv�ɕύX���������ꍇ�ɂ́A�͒ʎZ����܂���B
| �� �� �� �� �� |
���ݍ��ۂ�70�Έȏ�̉����ґS�������ꂼ��Z���ʼnېŏ���145���~�����̐l |
| �� �� �� �� II |
���ݍ��ۂ̉����ґS�����Z���Ŕ�ېł̐l |
| �� �� �� �� I |
���ݍ��ۂ̉����ґS�����Z���Ŕ�ېłŁA���̐��т̏���������ȉ��̐l |
| �� |
���@�̐H����͔�ی��҂����z�i�W�����S�z�j�S���A�c��͌��ݍ��ۂ����S���܂��B |
| �� |
�}�C�i�ی��i���j���������̏ꍇ
��Ë@�֓��Ń}�C�i�ی��i���j�𗘗p���Ď�f����ƁA��Ô�̎x���������ꂼ��̈�Ë@�֓��i���@�E�ʉ@�ʁj�Ŏ��ȕ��S���x�z�܂łƂȂ�܂��B |
| �� |
�}�C�i�ی��i���j���������łȂ��ꍇ
�I�����C�����i�m�F�ɂ�葋���ł̖{�l���ӂŁA�x���������ȕ��S���x�z�܂łƂȂ�܂��B�������A�I�����C�����i�m�F�����{���Ă��Ȃ���Ë@�֓��A�u���x�z�K�p�F��v�A�u���x�z�K�p�E�W�����S�z���z�F��v�̒����Ƃ߂�ꂽ�ꍇ�ɂ͌�t�\���葱�������Ă��������B�i��ʏ����ҁE�ېŏ������z690���~�ȏ�̐��тɑ�����l�͍���ҏ̒Ŏ��ȕ��S���x�z�܂łɂȂ�܂��̂ŁA�u���x�z�K�p�F��v�̔��s�͂ł��܂���B�j |
| �� |
70�Έȏ��70�Ζ����̎x�����v�z�����э��Z�̑ΏۂƂȂ�A���x�z��
70�Ζ����̎��ȕ��S���x�z���K�p����܂��B |
75�̒a�����̎��ȕ��S���x�z�i����[�u�j
�@���̓r����75�̒a�������}���A�u�������҈�Ð��x�v�Ɉڍs����l�̎��ȕ��S���x�z��75�̒a�����Ɍ���u70����74�̐l�̎��ȕ��S���x�z�v�̔��z�ɂȂ�܂��B
![���Ɍ����ݍ������N�ی��g�� ���ݎY�Ƃɏ]������g�����ƉƑ��̌��N����邽�߂̕ی��g���ł�](../share/images/title.gif)